※本記事は、以下の対談動画をもとに構成しています。
本対談では、AIセキュリティ代表の堀居隆生が、安部さんの歩んできたキャリアや、花王時代から続くデータ活用文化、生成AIがもたらす変革、そして「Security for AI」の未来について語り合いました。
安部 真行氏
1980年に花王株式会社へ入社。情報システム部門にてキャリアを重ね、2015年からはCIOおよびCISOとして全社のIT・セキュリティ戦略を推進。退任後はTOPPANエッジ(旧トッパン・フォームズ)でIT統括顧問を務め、複数社でITアドバイザーや社外取締役として経営と技術の橋渡しを担っている。
AI大企業の視点で読み解くAI時代の経営課題
堀居:
花王で執行役員を務められていた際には、どのような業務を担当されていたのでしょうか?
安部さん:
会社の執行役員で情報システムや情報セキュリティを担当するという役割ですので、はっきりいって会議ばかりやっているという感じです。だいたい一人1日8時間の枠があるとすると、30分刻みあるいは1時間刻みがありますが、頭の中のチャネルをそれに合わせて変えていくということが必要になります。今は一線から距離を置いていますので、逆にゆっくりものを考える時間があるのかなという気がしています。
堀居:
いろいろな記事も拝見させていただいたのですが、昨今のAIという潮流において、何か重なる部分を感じられることはありますか?
安部さん:
データを使って企業を経営していこうという流れは昔からあります。私がいた花王という会社は1980年代からマーケティングを数字で語っていく文化があったんです。だからAIが世の中に出てきたころから、アルゴリズムを考える研究所を作ったり、活用を進めていく基盤がありました。2000年代に入ってコンピュータの性能が上がってきて、アルゴリズムを実務に使えるようになった。生産活動の平準化や在庫の低減など、成果が出るようになっていきましたね。
大規模システムや新技術をCIOやCISOとして導入・推進する際の難しさとは
堀居:
大規模システムや新しい技術の導入を推進される際の難しさはどういう点ですか?
安部さん:
やはりお金がかかるというのが最大のポイントです。会社を成長させるには投資が必要ですが、情報や情報セキュリティへの投資はなかなか納得感を得にくい。情報システム部門の人はその説明責任を負っていますから、本当にご苦労されていると思います。経営にどう分かりやすく説明し、推進環境を整えるか──ここが非常に難しいところだと思います。
“セキュリティは明日を築く力になっていく”ということを経営層に伝えるには
堀居:
セキュリティを抑止力ではなく推進力と捉えていますが、経営者にその価値を伝える際に工夫されたエピソードはありますか?
安部さん:
セキュリティをプラスに捉えるコンサルは実は少ないんです。どうしても守りの発想になりがちです。でもBtoC企業では顧客の信頼が事業の根幹を支えていますよね。だからセキュリティが担保されていることをポジティブに打ち出し、マーケティングに活用するというサイクルができれば非常に良い成果を生むはずです。
堀居:
アドバイザリーで関わられている企業でも似たような課題を感じますか?
安部さん:
BtoBでも「サプライチェーンのセキュリティ」が重要になっています。事業は自社だけで完結しません。原材料を提供するベンダーや製品を販売する流通チャネルなど、必ず川上・川下につながる企業がある。そのどこかでインシデントが起きると流れ全体が滞ってしまうんです。だから自社だけでなく前後も安全を確認しましょう、というのが最近の潮流ですね。
─データ文化×生成AI─ 消費財業界に訪れる次の変革とは
堀居:生成AIは消費財業界にどんな変革をもたらすとお考えですか?
安部さん:これまではデータを読み取るのは人間で、自分の経験をベースに判断してきました。でも生成AIやアナリティクスのアルゴリズムを組み合わせることで、人間が気づかなかったデータの動きから新しい提案を生み出せる。流通に対する提案や新たな訴求活動につながります。特に非構造化データ、たとえば画像の領域は「きれい」「汚い」といった形容詞で語られてきました。生成AIはそれを“名詞に変換する”可能性がある。つまり曖昧な表現を定量的に扱えるようになるんです。これは非常に大きな変革だと思います。
安全なAIは“今”必要か、それとも未来の課題か
堀居:
安全なAIというのは今すぐ必要なものなのでしょうか? それとも未来の課題でしょうか?
安部さん:
二つあると思います。一つはセキュアな環境の中でどうAIを推進するかという従来型のセキュリティ。そしてもう一つは「誤差」をどう扱うかです。アルゴリズムには必ず誤差が生じる。95%、98%までは高められるけど、100%を目指すと事業がひっくり返るほどのコストがかかる。
だから重要なのは「誤差を前提に安心して使えるようにする」こと。どの程度誤差があるかをユーザーに認識してもらい、どこまで縮められるかを努力する。そのうえで事業の活動や計画に組み込むことが大事だと思います。
大企業のトップが選んだ次の挑戦 ─AIセキュリティ参画の舞台裏
堀居:
安部さんが弊社に参画されたきっかけを教えてください。
安部さん:
最初は偶然AIセキュリティさんを知ったのですが、堀居さんとお会いして「経営とセキュリティを一体で考える」という発想が非常に面白いと感じました。また、若い経営陣が社会課題に挑んでいる姿に共感したんです。自分の知見が役立つなら応援したいと思ったのが大きな理由です。
堀居:
AIセキュリティの魅力はどこにあると感じますか?
安部さん:
普通セキュリティ会社は自社プロダクト中心になりがちで、ピンポイントの解決策しか出せないことが多い。でもAIセキュリティさんは「経営×セキュリティ」を掲げ、診断からソリューション提案まで俯瞰的に取り組んでいる。ここが特徴的だと思います。
さらに1万人のフリーランスを抱えている点や、難関資格を持つシニアメンバーが集まっている点も強みですね。これだけの厚みを持ったチームはなかなかありません。
これからのAIセキュリティで最大のイシューとは
堀居:
弊社の強みは専門性と幅広さに加え、経験豊富なシニア人材の存在です。もう一つの武器として「AIセキュリティ」に取り組んでいますが、この領域が直面する大きな課題について、どのようにお考えでしょうか?
安部さん:
AIセキュリティさんの考え方に「Security for AI」がありますよね。多くの企業は「AI for Security」、つまりAIを使ってセキュリティを強化する方向に目を向けていますが、AIセキュリティさんは「AIのためのセキュリティ」を訴求している。ここは非常に大きな強みだと思います。
また、以前エンジニアの方と同席したとき、人材の発掘力の高さに驚きました。どうやってこうした優秀な人材を集めているのか、むしろ伺いたいですね。
堀居:
弊社のコアコンピタンスの一つに「1万名のフリーランスネットワーク」があります。プロジェクトごとに弊社の社員がPMを務め、フリーランスと協力して進めています。その中で「面白い」と評価いただいたり、信頼できる人材とのつながりが深まり、リクルーティングにもつながっています。
安部さん:
創業からまだ長い期間は経っていませんが、その中で1万名のフリーランスを抱えられるというバイタリティは、大きな魅力だと思いますね。
Security for AI時代の課題
堀居:
AI導入においては、誰がどこまで責任を持つのかといった“責任分界点”が難しいという声を企業からよく伺います。この課題はどのような背景から生じているとお考えですか?
安部さん:
「業務としての歴史」が大きく影響していると思います。経理や法務、製造などは何百年もの歴史があり、体系化や知識の蓄積があります。しかし情報システムや情報セキュリティは、起源がせいぜい第2次世界大戦以降。数十年しか積み重ねがなく、その進歩も非常に速い。
そのため、従来の業務のように「過去の知見で対応する」ことが難しく、責任範囲を明確にするのも困難なんです。だからこそ、情報システムやセキュリティの専門家と、現場の実務担当者が議論を重ねて「Security for AIの責任分界点」をこれから一緒に作り上げていく時代になっているのだと思います。
堀居:
会計や法務など各部門が独自に生成AIを導入し始めており、PoC(実証実験)レベルで動いているケースも増えています。管理の目が届かず“シャドーAI”化する懸念もある中で、これに風穴を開ける一手は何でしょうか?
安部さん:
情報システム部門が閉じすぎていることが一因だと思います。新しい技術は「どう活かせるか」をオープンに議論し、自由に使ってもらう一方で「使ったら報告してほしい」という文化を築くことが重要です。そうすればセキュリティ面で危険があった場合も、「橋を作ってから渡ろう」「迂回しよう」と具体的に助言できます。部門間のコミュニケーションを円滑にする風土が整えば、真の意味でのSecurity for AIにつながるはずです。
Security for AI推進の鍵 ─AIセキュリティ社が注力すべきこと
堀居:
AIの潮流は止められず、PwCさんやマッキンゼーさんの調査でも大きな経済効果や生産性向上が示されています。その一方でセキュリティリスクは確実に存在します。AIセキュリティとして「Security for AI」を推進する上で、どの領域に注力し、どのような思想で取り組むべきでしょうか。
安部さん:
AIは今後10年で不可欠なツールになっていきますが、同時に危険も孕んでいます。そのリスクをわかりやすく経営層や事業部門に伝え、文化的に「安全なAI活用」を広めていくことが大切です。AIセキュリティには、ツール導入だけでなく啓蒙や発信を通じて企業とのコミュニケーションを促進していただきたい。それが結果的にビジネスにもつながっていくと考えています。
堀居:
そういった発信を弊社の戦略としても進め、コンサルタントやエンジニアのマインドにも取り入れていこうと思います。




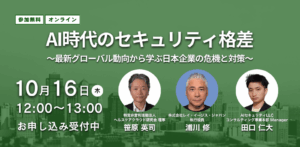


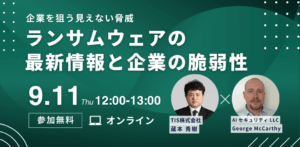
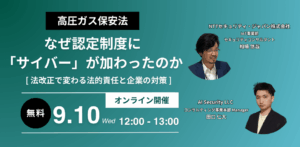

コメント