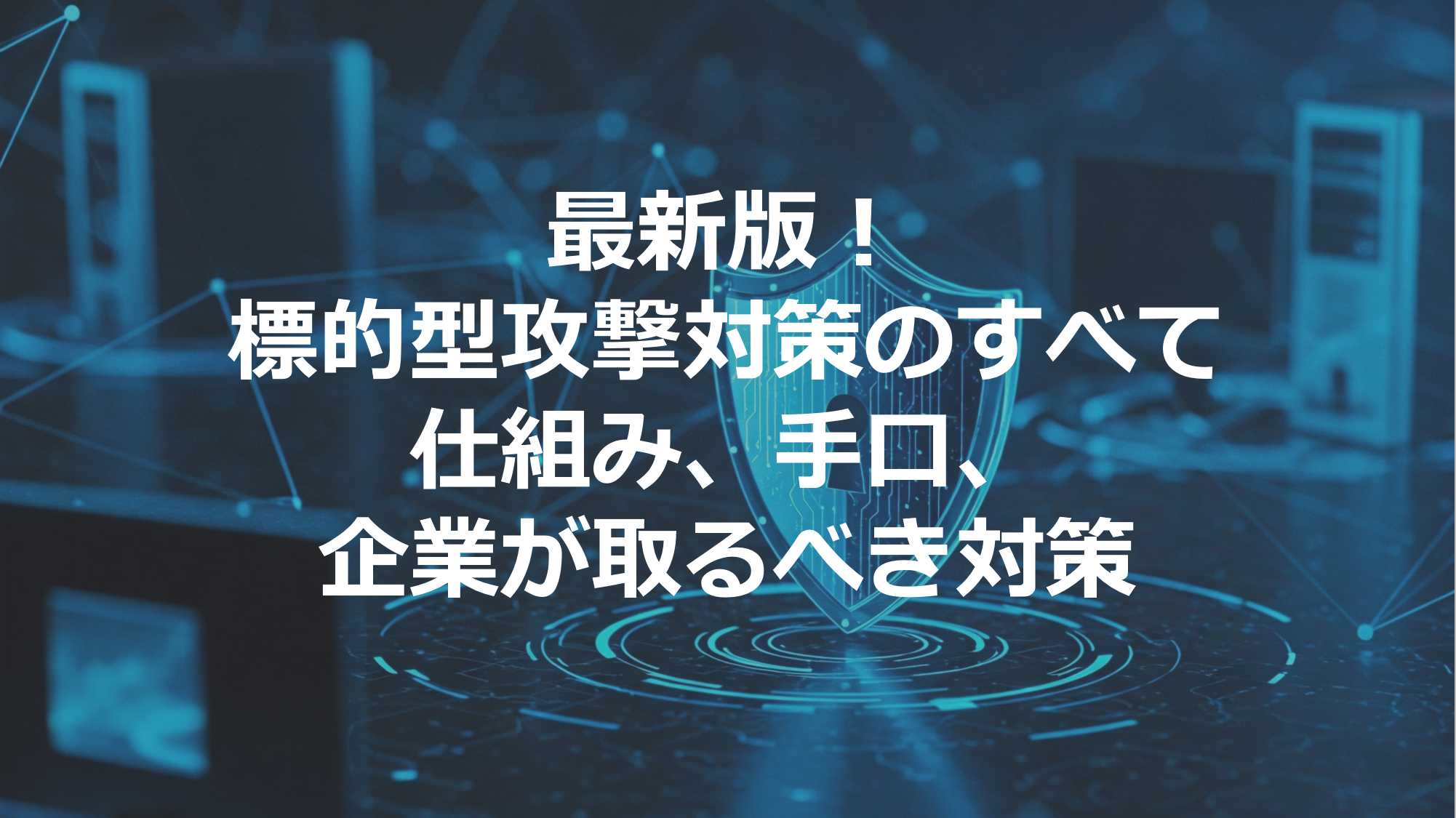標的型攻撃とは?その仕組みと脅威
標的型攻撃の定義と目的
標的型攻撃は、特定の組織や個人を狙い、機密情報の窃取やシステム破壊を目的とするサイバー攻撃です。無差別型攻撃とは異なり、攻撃者はターゲットを詳細に調査し、巧妙な手口で侵入を試みます。 標的型攻撃は、その精密さと隠蔽性の高さから、従来のセキュリティ対策をすり抜けることが多く、企業や組織にとって深刻な脅威となっています。 攻撃者は、ターゲットの内部情報を事前に調査し、その情報を基にカスタマイズされた攻撃を仕掛けるため、一般的な防御策では検知が困難な場合があります。 標的型攻撃の目的は、単なるデータの窃取にとどまらず、企業の評判を貶めたり、重要なシステムを停止させたりするなど、組織に深刻な損害を与えることもあります。 近年では、国家が関与する高度な標的型攻撃も確認されており、その脅威はますます深刻化しています。企業は、標的型攻撃の脅威を認識し、適切な対策を講じる必要があります。 標的型攻撃の対策は、技術的な対策だけでなく、従業員のセキュリティ意識の向上や、インシデント発生時の対応策の準備など、多岐にわたる取り組みが必要です。
標的型攻撃の典型的なシナリオ
標的型攻撃は、reconnaissance(偵察)、weaponization(武装化)、delivery(配信)、exploitation(脆弱性の利用)、installation(インストール)、commandandcontrol(C&C)、actionsonobjectives(目的の実行)の7つの段階を経て実行されます。攻撃者は、まずターゲットの情報を収集し、脆弱性を特定します。次に、脆弱性を悪用するマルウェアを作成し、メールやWebサイトを通じて配信します。マルウェアがターゲットのシステムに侵入すると、機密情報を窃取したり、システムを破壊したりします。 攻撃者は、公開されている情報だけでなく、ソーシャルメディアや従業員の個人的なブログなども利用して、ターゲットに関する情報を収集します。収集した情報を基に、攻撃者はターゲットの興味や関心を引くようなメールを作成し、マルウェアを添付したり、不正なWebサイトへのリンクを埋め込んだりします。 マルウェアがターゲットのシステムに侵入すると、攻撃者はC&Cサーバーを通じてマルウェアを制御し、機密情報の窃取やシステム破壊などの目的を実行します。攻撃者は、長期間にわたってシステムに潜伏し、徐々に活動範囲を広げていくこともあります。 標的型攻撃の初期段階である偵察活動を早期に検知し、対策を講じることが重要です。また、マルウェアの侵入を検知し、感染拡大を防ぐための対策も必要です。
標的型攻撃による被害事例
過去には、日本年金機構やGoogleなどが標的型攻撃の被害に遭っています。これらの事例から、標的型攻撃はあらゆる組織にとって脅威となり得ることを理解する必要があります。 日本年金機構の事例では、標的型メール攻撃によって職員のPCがマルウェアに感染し、大量の個人情報が漏洩しました。この事件は、国民の年金記録という重要な情報が漏洩したことで、社会的な信頼を大きく損なう結果となりました。 Googleの事例では、中国政府の関与が疑われるハッカー集団が、Googleのシステムに侵入し、知的財産を窃取しました。この事件は、国家が関与するサイバー攻撃の脅威を改めて認識させるものとなりました。 これらの事例から、標的型攻撃は、規模や業種に関わらず、あらゆる組織が標的となり得ることを示しています。企業は、自社のセキュリティ対策の現状を把握し、標的型攻撃に対する備えを強化する必要があります。 また、インシデントが発生した場合に備え、迅速かつ適切な対応策を講じることができるように、インシデントレスポンス体制を構築しておくことが重要です。
標的型攻撃の主な手口
標的型メール攻撃(スピアフィッシング)
標的型メール攻撃は、特定の組織や個人を装い、マルウェアが添付されたメールや不正なWebサイトへのリンクを送信する手口です。受信者を信用させるために、実在する人物や組織の名前、役職などを悪用することがあります。 攻撃者は、ターゲットの興味や関心を引くような件名や本文を作成し、受信者にメールを開封させようとします。例えば、請求書、注文書、人事通達などを装ったメールがよく利用されます。 メールに添付されたファイルは、PDF、Word、Excelなどの形式を装っていることが多いですが、実際にはマルウェアが埋め込まれています。また、メール本文に記載されたURLをクリックすると、不正なWebサイトに誘導され、マルウェアがダウンロードされたり、個人情報が盗まれたりする可能性があります。 標的型メール攻撃は、非常に巧妙な手口で実行されるため、一般的なセキュリティ対策では検知が困難な場合があります。従業員は、不審なメールに注意し、添付ファイルを開いたり、URLをクリックしたりする前に、送信元を確認するなど、慎重な対応を心がける必要があります。 また、企業は、標的型メール攻撃対策として、メールセキュリティゲートウェイの導入や、従業員へのセキュリティ教育の徹底などの対策を講じる必要があります。
水飲み場型攻撃
水飲み場型攻撃は、ターゲットが頻繁にアクセスするWebサイトを改ざんし、マルウェアを仕込む手口です。ターゲットがWebサイトにアクセスすると、マルウェアが自動的にダウンロードされ、システムに感染します。 攻撃者は、ターゲットが利用する可能性の高いWebサイトを特定し、そのWebサイトの脆弱性を悪用して改ざんします。改ざんされたWebサイトには、マルウェアをダウンロードさせるための不正なコードが埋め込まれます。 ターゲットが改ざんされたWebサイトにアクセスすると、Webブラウザの脆弱性を悪用して、マルウェアが自動的にダウンロードされ、システムに感染します。マルウェアは、バックグラウンドで動作し、ユーザーに気づかれることなく、機密情報を窃取したり、システムを破壊したりします。 水飲み場型攻撃は、ターゲットが信頼しているWebサイトを悪用するため、防御が非常に困難です。Webサイトの運営者は、常にWebサイトのセキュリティ対策を強化し、脆弱性を早期に修正する必要があります。 また、Webサイトの利用者は、WebブラウザやOSを常に最新の状態に保ち、セキュリティソフトを導入するなど、自己防衛策を講じる必要があります。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、ターゲットの取引先や関連会社を攻撃し、そこからターゲットに侵入する手口です。セキュリティ対策が脆弱な企業を踏み台にすることで、より大規模な攻撃が可能になります。 攻撃者は、ターゲット企業との取引関係にある企業の中で、セキュリティ対策が比較的脆弱な企業を狙います。その企業のシステムに侵入し、マルウェアを感染させたり、機密情報を窃取したりします。 そして、その企業を踏み台にして、最終的なターゲットである企業への攻撃を仕掛けます。例えば、取引先の企業から送られてくるメールにマルウェアを添付したり、取引先の企業のシステムを経由してターゲット企業のシステムに侵入したりします。 サプライチェーン攻撃は、ターゲット企業だけでなく、サプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性があります。そのため、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策の強化が重要です。 企業は、自社のセキュリティ対策だけでなく、取引先の企業のセキュリティ対策状況も把握し、必要に応じて支援を行う必要があります。また、サプライチェーン全体での情報共有体制を構築し、脅威情報を共有することも重要です。
企業が取るべき標的型攻撃対策
従業員へのセキュリティ教育の徹底
標的型メール攻撃の手口や、不審なWebサイトの見分け方など、従業員へのセキュリティ教育を徹底することが重要です。定期的な研修や模擬訓練を実施し、セキュリティ意識を高めましょう。 従業員は、企業のセキュリティ対策の最後の砦です。従業員一人ひとりがセキュリティ意識を高め、適切な行動を取ることで、標的型攻撃による被害を最小限に抑えることができます。 セキュリティ教育では、標的型メール攻撃の手口や、不審なメールの見分け方、添付ファイルを開く際の注意点、URLをクリックする際の注意点などを具体的に説明します。 また、模擬訓練を実施することで、従業員が実際に標的型メール攻撃に遭遇した場合の対応を練習することができます。従業員が不審なメールを発見した場合の報告手順や、インシデント発生時の対応手順なども周知徹底します。 セキュリティ教育は、一度実施するだけでなく、定期的に実施し、従業員のセキュリティ意識を常に高く保つことが重要です。また、最新の脅威動向に合わせて、教育内容を更新することも重要です。
OS・ソフトウェアの最新化
OSやソフトウェアの脆弱性を悪用した攻撃を防ぐために、常に最新の状態に保つことが重要です。自動アップデート機能を有効にし、セキュリティパッチを適用しましょう。 OSやソフトウェアには、セキュリティ上の脆弱性が存在することがあります。攻撃者は、これらの脆弱性を悪用して、システムに侵入したり、マルウェアを感染させたりします。 OSやソフトウェアのベンダーは、脆弱性が発見されると、セキュリティパッチを公開します。セキュリティパッチを適用することで、脆弱性を修正し、攻撃のリスクを低減することができます。 OSやソフトウェアのアップデートは、手動で行うこともできますが、自動アップデート機能を有効にしておくと、自動的に最新の状態に保つことができます。 企業は、OSやソフトウェアのアップデート管理を徹底し、常に最新の状態に保つように努める必要があります。また、使用していないソフトウェアは、削除することも有効な対策です。
セキュリティソフト・サービスの導入
セキュリティソフトや、標的型攻撃対策に特化したFireEye(Trellix)のようなサービスの導入は、マルウェアの侵入を防ぐ上で有効です。エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、メールセキュリティなど、多層的な対策を講じましょう。 セキュリティソフトは、マルウェアの侵入を検知し、駆除することができます。また、不正なWebサイトへのアクセスをブロックしたり、不審なファイルの実行を阻止したりする機能も備えています。 標的型攻撃対策に特化したサービスは、高度な分析技術を用いて、標的型攻撃の兆候を検知し、攻撃を阻止することができます。これらのサービスは、セキュリティソフトでは検知できないような、巧妙な攻撃を検知するのに役立ちます。 エンドポイントセキュリティは、PCやスマートフォンなどのエンドポイントデバイスを保護するための対策です。ネットワークセキュリティは、ネットワークを介した攻撃からシステムを保護するための対策です。メールセキュリティは、メールを介した攻撃からシステムを保護するための対策です。 企業は、これらのセキュリティ対策を組み合わせ、多層的な防御体制を構築する必要があります。
インシデント発生時の対応策の準備
万が一、標的型攻撃の被害に遭った場合に備え、インシデントレスポンス計画を策定しておくことが重要です。被害状況の把握、感染拡大の防止、復旧作業の手順などを明確にしておきましょう。 インシデントレスポンス計画とは、セキュリティインシデントが発生した場合に、迅速かつ適切に対応するための計画です。インシデントレスポンス計画には、インシデントの定義、責任者の役割、対応手順などが記載されます。 インシデントが発生した場合、まず被害状況を把握することが重要です。どのシステムが影響を受けているのか、どのような情報が漏洩した可能性があるのかなどを調査します。 次に、感染拡大の防止策を講じます。感染したシステムをネットワークから隔離したり、マルウェアを駆除したりします。また、他のシステムへの感染を防ぐために、注意喚起を行ったり、アクセス制限をかけたりします。 最後に、システムの復旧作業を行います。バックアップデータからシステムを復元したり、セキュリティパッチを適用したりします。また、再発防止策を講じることも重要です。 企業は、インシデントレスポンス計画を定期的に見直し、最新の状態に保つ必要があります。また、インシデントレスポンスチームを組織し、定期的に訓練を実施することで、インシデント発生時の対応能力を高めることができます。
UTM・WAFの導入
UTM(統合脅威管理)やWAF(Webアプリケーションファイアウォール)を導入することで、ネットワークの入り口で不正な通信を遮断し、Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃を防ぐことができます。 UTMは、ファイアウォール、IDS/IPS(侵入検知/防御システム)、アンチウイルス、アンチスパムなどの複数のセキュリティ機能を統合したアプライアンスです。UTMを導入することで、ネットワークの入り口で不正な通信を遮断し、マルウェアの侵入を防ぐことができます。 WAFは、Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃を防ぐためのファイアウォールです。SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなどの攻撃からWebアプリケーションを保護することができます。 Webアプリケーションは、インターネット経由でアクセスできるため、攻撃者にとって格好の標的となります。WAFを導入することで、Webアプリケーションのセキュリティを強化し、情報漏洩やサービス停止などのリスクを低減することができます。 企業は、UTMとWAFを適切に組み合わせ、ネットワークとWebアプリケーションのセキュリティを強化する必要があります。
まとめ:標的型攻撃対策は継続的な取り組みが重要
標的型攻撃は、常に進化し続けるため、一度対策を講じたからといって安心はできません。最新の脅威動向を把握し、継続的に対策を強化していくことが重要です。従業員教育、OS・ソフトウェアのアップデート、セキュリティソフトの導入など、多層的な対策を講じ、組織全体のセキュリティレベルを向上させましょう。 標的型攻撃は、攻撃手法が高度化しており、従来のセキュリティ対策では防御が困難な場合があります。そのため、常に最新の脅威動向を把握し、自社のセキュリティ対策の弱点を洗い出し、対策を強化していく必要があります。 従業員教育は、セキュリティ対策の基本です。従業員一人ひとりがセキュリティ意識を高め、不審なメールやWebサイトに注意することで、標的型攻撃による被害を未然に防ぐことができます。 OSやソフトウェアのアップデートは、脆弱性を修正し、攻撃のリスクを低減するために重要です。セキュリティソフトは、マルウェアの侵入を検知し、駆除することができます。 これらの対策を組み合わせ、多層的な防御体制を構築することで、標的型攻撃に対する防御力を高めることができます。また、インシデント発生時の対応策を準備しておくことで、万が一被害に遭った場合でも、迅速かつ適切に対応することができます。 標的型攻撃対策は、継続的な取り組みが重要です。定期的にセキュリティ対策を見直し、最新の脅威動向に合わせて対策を強化していくことで、組織全体のセキュリティレベルを向上させることができます。